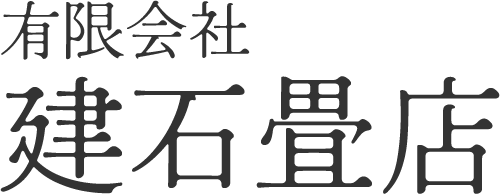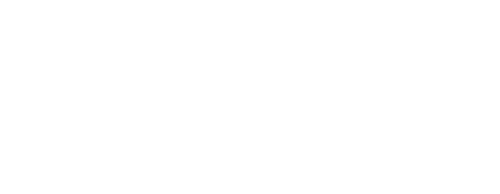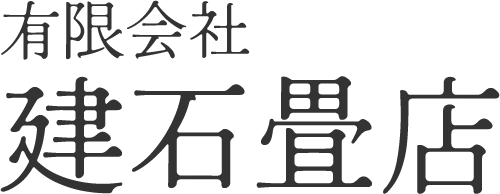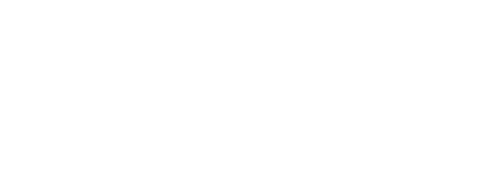畳替えの手順と費用相場を解説DIYや業者選びのポイントも紹介
2025/11/05
畳替えの手順で悩んでいませんか?和室の快適さや美観を保つために畳替えは欠かせませんが、「費用はどのくらいかかるのか」「自分でDIYはできるのか」「業者選びのコツは?」など、検討すべきポイントは多岐にわたります。畳替えには畳表や裏返し、新調など種類があり、手順や注意点を正しく知ることが失敗を防ぐ第一歩。本記事では畳替えの具体的な手順から、費用相場、DIYでのチャレンジ方法、信頼できる業者選びのポイントまで徹底解説します。迷いがちな予算や仕上がり、作業日程などの疑問を解消し、ご自宅に合った最適な畳替えを実現できる知識と方法が手に入ります。
目次
畳替え手順を分かりやすく解説

畳替えの始め方と事前準備の流れを解説
畳替えを始める際は、まず畳の現状確認からスタートします。畳表や畳床の劣化具合、シミやカビの有無をチェックし、表替え・裏返し・新調のどれが最適かを判断しましょう。畳替えの種類によって費用や作業内容が大きく異なるため、事前に正確な状態把握が重要です。

畳替え手順の基本と必要な道具を確認しよう
畳替えの基本手順は「畳の取り外し」→「畳表・畳床の確認」→「新しい畳表への張り替え」→「畳の設置」という流れが一般的です。まず、部屋から畳を一枚ずつ丁寧に取り出し、床や下地の状態も合わせてチェックします。

和室の畳替えで押さえるべき作業ポイント
和室の畳替えでは、畳の種類や使用目的に応じた作業ポイントを押さえることが大切です。例えば、一般的な表替えでは、今使っている畳床をそのまま活かし、畳表と縁だけを新しくします。一方、畳床まで傷んでいる場合は新調が必要です。
畳替えの際は、部屋全体のバランスや家具の配置も考慮しましょう。特に畳の寸法や向きが揃っていないと、隙間や段差が生じやすくなります。施工後に家具を元に戻す際は、畳表の傷や凹みを防ぐためにフェルトやマットを敷くのがおすすめです。
また、湿気やカビ対策として、作業前後に部屋の換気や床下の清掃を行うと、畳の寿命が延びます。和室本来の快適さを維持するためにも、気候や生活スタイルに合った畳表・縁を選び、定期的なメンテナンスも忘れずに行いましょう。

畳替え手順で失敗しないための注意点まとめ
畳替えでよくある失敗例には、寸法違いや畳表のたるみ、縁のズレなどがあります。これらは、作業前の確認不足や道具の使い方の誤りが原因となることが多いです。事前に畳の寸法を正確に測り、必要な材料を余裕をもって準備しましょう。
また、DIYでチャレンジする場合は、畳表や縁の固定が甘いと、使用中にズレや剥がれが発生しやすくなります。作業は必ず手順通りに進め、力加減や位置合わせに注意が必要です。初めての場合は、練習用の畳や小さなスペースで試してみるのもおすすめです。
業者に依頼する場合でも、作業内容や納期、費用の内訳を事前に確認し、見積もりの比較や口コミのチェックを行いましょう。万が一のトラブルを避けるためにも、疑問点は事前に相談し、不明点を残さないことが大切です。

畳替えの順番と作業日数の目安を知って安心
畳替えの順番は、一般的に「裏返し」→「表替え」→「新調」と進みます。畳の状態が良ければ裏返しで延命でき、表面の劣化が目立つ場合は表替え、それでも改善しない場合は新調が必要です。畳替えの種類によって作業内容が異なるため、順番を理解しておくと計画が立てやすくなります。
作業日数の目安は、6畳程度の表替えや裏返しなら半日から1日、新調の場合は2日程度が一般的です。ただし、業者の混雑状況や特殊な素材を使用する場合は日数が延びることもあります。DIYの場合は慣れていないと時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
畳替えの順番や日数を把握することで、和室の使用予定や家具の移動計画も立てやすくなります。特に家族が多いご家庭や、来客予定がある場合は、事前にスケジュール調整を行い、快適な空間作りを目指しましょう。
和室の快適さアップ畳替えの流れ

畳替え手順で快適な和室を実現する方法
畳替えは和室の快適さや美観を保つうえで欠かせない作業です。畳替え手順を正しく理解することで、失敗を防ぎ、理想の和室空間を実現できます。まずは畳表替えや裏返し、新調といった畳替えの種類を把握し、ご自宅の畳の状態や使用年数に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
畳替えの主な流れは、畳の状態確認→畳の取り外し→表替えや裏返し作業→再設置となります。畳表や縁のデザイン選びもポイントで、和室の印象を大きく左右します。DIYでの畳替えも可能ですが、寸法測定や畳表の張り替え作業には慎重さと道具が必要です。特に初めての方や広範囲の交換は、信頼できる業者への依頼も検討しましょう。
畳替え時は、作業中の家具移動や部屋の清掃、換気なども重要な準備事項です。業者依頼の場合は、作業日数や費用、施工内容の確認を事前に行いましょう。6畳程度の一般的な和室なら、作業は半日から1日程度で完了するケースが多いです。

畳替えで和室の雰囲気が変わる理由と注意点
畳替えを行うことで、和室全体の雰囲気が一新されます。新しい畳表は色鮮やかで香りも良く、部屋を明るく清潔な印象に変えてくれます。特にモダンな縁や琉球畳など、デザイン性の高い素材を選ぶことで、従来の和室から現代的な空間にもアレンジ可能です。
畳替え時の注意点として、畳表や縁の素材選びが挙げられます。い草や和紙など、素材ごとに耐久性やメンテナンス性が異なるため、家族構成やライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。また、湿気やカビ対策として、抗菌・防カビ加工された畳表を選ぶと、長期間快適に使用できます。
畳替えの際は、家具の重さや部屋のサイズに合った畳選び、また畳の寸法測定ミスにも注意が必要です。DIYの場合は特に、作業前に十分な情報収集と準備を行い、必要に応じて専門業者に相談しましょう。

畳替え後の和室メンテナンスポイントを解説
畳替え後の和室を長く快適に保つには、定期的なメンテナンスが欠かせません。新しい畳表は湿気を吸収しやすいため、換気と日光を適度に取り入れてカビやダニの発生を防ぎましょう。特に梅雨時期や冬場の結露対策が重要です。
畳表の汚れは、乾いた布で軽く拭き取るのが基本です。水拭きは畳の劣化を早める原因となるため控えましょう。また、畳表の傷みや色あせが目立ってきた場合は、裏返しや表替えのタイミングです。畳の隙間やへこみが気になったら、早めに業者へ相談することで大きなトラブルを防げます。
小さなお子様やペットがいるご家庭では、畳表の耐久性や抗菌性にも注目し、必要に応じて適切なメンテナンス方法を取り入れましょう。定期点検・掃除を習慣化することで、和室の美観と快適さを長く保つことができます。

畳替えの流れで和室の美観を保つ秘訣
畳替えの流れを理解し、正しい手順で行うことが和室の美観維持に直結します。まずは畳の状態確認から始め、畳表や縁の傷み・汚れをチェックしましょう。畳の取り外しや新しい畳表の選定、裏返しの可否判断など、各工程でプロの目線が重要となります。
畳替え作業では、寸法測定や畳の敷き方にも注意が必要です。施工ミスによる隙間や段差の発生を防ぐため、事前の準備と確認作業は入念に行いましょう。DIYで行う場合も、ホームセンターで専用の道具や材料を揃え、手順書や動画を参考に進めるのが失敗を防ぐポイントです。
また、業者依頼時は見積もり内容や作業日程、施工後のアフターサービスまで確認しましょう。信頼できる業者選びが、仕上がりの美しさと長持ちの秘訣です。実際の利用者の口コミや実績も参考にすると安心です。

畳替えで和室の快適さが向上する要素とは
畳替えによって和室の快適性が大きく向上します。新しい畳表は吸湿性や断熱性に優れ、夏は涼しく冬は暖かい室内環境を実現できます。また、い草の香りはリラックス効果があり、心地よい空間づくりに役立ちます。
防カビ・抗菌加工された畳表や和紙畳など、現代的な機能素材を選ぶことで、アレルギー対策やお手入れのしやすさも向上します。ペットや小さなお子様がいるご家庭では、耐久性や汚れに強い素材を選ぶと安心です。さらに、畳替えの際に床下の通気や断熱材の追加も検討すると、快適性が一層高まります。
畳替えは単なるリフォームではなく、住まい全体の健康や家族の暮らしやすさに直結する大切な作業です。定期的な畳替えで、和室本来の機能と心地よさを最大限に引き出しましょう。
自分でできる畳替えの基本方法とは

自分で畳替えする手順と必要な道具を紹介
自分で畳替えを行う場合、まず必要な道具をしっかり揃えることが重要です。主に使う道具は、畳を持ち上げるためのてこ棒、畳の縁を固定するためのタッカーや釘抜き、カッター、メジャーなどがあります。これらの道具はホームセンターや専門店で購入でき、DIY初心者でも扱いやすいものが多いです。
畳替え手順の基本は、まず部屋の家具や障害物を移動させて作業スペースを確保し、既存の畳を慎重に取り外すことから始まります。その後、畳表の状態や裏返しの可否を確認し、必要に応じて新しい畳表や畳縁を準備します。作業中は畳床を傷つけないよう注意が必要です。
特に、畳を元の位置に戻す際に寸法の違いや隙間が生じやすいため、元の配置を写真で記録しておくと失敗防止につながります。道具の使い方や手順を事前に理解し、準備を怠らないことが自分で畳替えを成功させるポイントです。

DIY畳替えの基本的な流れと作業ポイント
DIYで畳替えを行う場合、基本的な流れを把握しておくことが大切です。主な手順は、①家具の移動 ②畳の取り外し ③畳表・畳縁の交換または裏返し ④畳の再設置 となります。この順番を守ることで、作業の効率と仕上がりの質が向上します。
作業時のポイントとして、畳表を交換する際は畳床の状態を必ずチェックし、劣化やカビがあれば補修や新調も検討しましょう。また、畳縁の取り付けにはタッカーや専用釘を使用し、まっすぐに仕上げることで見栄えが大きく変わります。畳の裏返しの場合も、端部のめくれやすさに注意が必要です。
実際のユーザーからは、「表替えや裏返しは思ったより簡単だったが、畳の戻し位置を間違えて隙間ができた」という声もあるため、畳の配置管理が肝心です。流れごとに写真やメモを活用し、焦らず丁寧に進めましょう。

畳替えを自分で行う際の失敗しないコツ
自分で畳替えをする際に失敗を防ぐコツは、事前準備の徹底と一つ一つの作業を丁寧に行うことです。特に畳のサイズや配置をしっかり記録し、元の位置に正確に戻すことが隙間や段差を防ぐポイントとなります。
畳表や畳縁の選び方も重要で、和紙や樹脂素材の畳表を選ぶと耐久性やメンテナンス性が向上します。作業中は畳床の状態を確認し、カビや傷みがひどい場合は無理に再利用せず、部分補修や新調も検討しましょう。また、畳縁の固定には力加減や位置合わせに注意し、仕上がりを美しく保つ工夫が求められます。
初心者がやりがちな失敗例として、畳を無理に曲げてしまい畳床を傷めるケースや、縁のずれによる見た目の悪化が挙げられます。これらを防ぐため、作業マニュアルや動画を参考にしながら、慎重に進めることが大切です。

初心者向け畳替えの手順と注意する点
畳替え初心者の方は、まず畳表替え・裏返し・新調の違いを理解することから始めましょう。表替えは畳表のみを新しくする方法、裏返しは既存の畳表を裏返して再利用する方法、新調は畳床ごと交換する方法です。和室の状態や畳の劣化度合いに合わせて最適な方法を選択しましょう。
作業の際は、畳を持ち上げる際に手や腰を痛めないよう、てこ棒や軍手を使うのが安全です。また、畳表の交換や裏返し時は、畳床のカビやシミ、虫食いの有無を必ず確認し、異常があればその場で対処することが大切です。特に湿度が高い時期はカビの発生リスクが高まるため、換気や乾燥を心がけましょう。
初心者の方でも、作業前に手順を整理し、道具や材料を揃えておけばスムーズに畳替えができます。また、不安な場合は一部分だけ試してみる、または専門業者に相談するのもおすすめです。

自分で畳替えする場合の手順解説
自分で畳替えを行う場合の基本手順は、①家具の移動 ②畳の取り外し ③畳表・縁の取り替えまたは裏返し ④畳の再設置 ⑤清掃・仕上げ となります。各工程で丁寧な作業を心がけることで、トラブルの発生を防ぎます。
畳を持ち上げる際は、てこ棒を使って慎重に作業し、畳床やフローリングを傷つけないよう配慮しましょう。畳表や縁を交換する際は、サイズのズレや縁の浮きに注意し、しっかりと固定します。裏返しの場合も、畳表の状態をよく確認してから作業に取りかかることが大切です。
作業を終えたら、畳の隙間や段差、浮きがないか最終チェックを行い、必要に応じて微調整します。作業時間は6畳でおよそ数時間程度が目安ですが、初めての場合は余裕を持って行うと安心です。失敗を防ぐためにも、手順を守りながら慎重に進めてください。
畳の裏返しや新調を選ぶ目安を知ろう

裏返しや新調どちらを選ぶ畳替え判断基準
畳替えを検討する際、「裏返し」と「新調」のどちらを選ぶべきか迷う方が多いです。結論から言うと、畳表の傷み具合や畳床(たたみどこ)の状態によって最適な方法が異なります。例えば、畳表の色あせや軽度の汚れであれば裏返しが有効ですが、畳床まで傷んでいる場合は新調が必要です。
裏返しは、畳表をひっくり返して再利用する方法で、費用を抑えつつ美観を回復できる点がメリットです。一方、新調は畳全体を新しくするため、耐久性や快適性が大きく向上します。判断時には、畳の表面だけでなく、踏んだ時の沈みやヘタリ、カビや異臭の有無なども確認しましょう。
失敗しないためには、畳業者や専門家に現地で畳の状態を確認してもらうのが安心です。特に築年数が経過した住宅や、湿気の多い環境では、畳床の劣化リスクが高まるため注意が必要です。

畳替えで裏返しと新調の違いを理解しよう
畳替えには大きく分けて「裏返し」と「新調」の2種類があります。それぞれの違いを理解することが、最適な畳替えを選ぶ第一歩となります。裏返しは既存の畳表を裏面にして張り直す方法で、表面の傷みが軽度な場合に適しています。費用も比較的安価で、作業時間も短いのが特徴です。
一方、新調は畳床から畳表まで全て新しく作り直す方法です。長年使用して畳床がへたっている、カビや臭いが気になる場合などは新調が必要となります。新調は費用がかかりますが、和室の快適性や耐久性が大幅に向上します。
具体的な選択例として、裏返しは畳交換から3~5年程度で行うのが目安です。新調は10年以上経過し、畳表も畳床も劣化が目立つ場合に推奨されます。両者の違いを理解し、住まいの状況に合わせて選択しましょう。

畳替え手順に応じた作業内容の見極め方
畳替えの手順は、裏返しと新調で異なります。裏返しの場合は、畳を取り外して畳表を裏面に張り替え、再設置する流れです。新調の場合は、採寸・発注・製作・設置まで一連の工程が必要となります。
作業内容を見極めるポイントは、畳表や畳床の状態チェックです。畳表にシミや破れが多い場合や、畳床に沈みやカビが見られる場合は、裏返しでは不十分なことがあります。特にDIYでの作業を考える場合は、畳の重さや道具の準備、正確な採寸が求められるため、初心者には難易度が高い点も注意が必要です。
一方、業者に依頼する場合は、事前に現地調査と見積もりを依頼し、作業内容や費用、作業日程をしっかり確認しましょう。失敗を防ぐためには、畳の状態に応じた最適な手順を選択することが大切です。

裏返しや新調のタイミングと判断ポイント
畳替えのタイミングは、快適な和室環境を維持するために重要です。一般的に、裏返しは畳表の交換から3~5年、新調は10年以上が経過した場合が目安となります。畳表の色あせやささくれ、畳床の沈みやカビ、異臭が出てきたら交換を検討しましょう。
判断ポイントとしては、畳表の表面の状態だけでなく、畳床の弾力や異常音、湿気によるカビの有無などをチェックすることが大切です。特にペットや小さなお子さまがいるご家庭では、衛生面も重視して早めの交換をおすすめします。
実際の事例として、定期的な裏返しや新調を行うことで、和室の美観や快適性が長持ちしたといった声も多く聞かれます。畳の状態を定期的に確認し、適切なタイミングでメンテナンスを行いましょう。

畳替えの種類とおすすめの選び方について
畳替えには主に「裏返し」「表替え」「新調」の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、住まいや用途に合った選び方をすることが大切です。裏返しはコストを抑えたい方や、表面の傷みが少ない場合に適しています。表替えは畳床をそのまま活かしつつ、畳表だけを新しくする方法で、一般的なメンテナンスとして最も多く利用されています。
新調は、畳床まで劣化している場合や、リフォームで和室の印象を一新したい場合におすすめです。選び方のポイントは、畳の状態やライフスタイル、予算に応じて最適な方法を選ぶことです。例えば、耐久性やデザイン性を重視するなら、和紙畳やカラー畳など新素材を検討するのも一案です。
業者選びの際は、実績や口コミ、見積もり内容を比較し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。自分でDIYに挑戦する場合は、ホームセンターの商品や専門道具の準備、作業手順の確認をしっかり行いましょう。
DIY畳替えチャレンジの注意ポイント

DIYで畳替え手順を進める際の注意点まとめ
畳替えをDIYで行う場合、作業の流れや注意点を事前に把握することが重要です。畳には表替え・裏返し・新調といった種類があり、それぞれ必要な手順や準備が異なります。作業前には畳表や畳縁の素材、畳の寸法を正確に確認し、適切な道具を揃えましょう。
また、畳替え作業は家具の移動や古い畳の処分も伴うため、作業スペースの確保や処分方法の事前確認も欠かせません。畳表や畳床の状態によってはDIYよりも業者依頼が適している場合もあるため、状態チェックは慎重に行いましょう。

自分で畳替えするときの作業ミス予防法
自分で畳替えを行う際は、寸法ミスや畳表・縁の取り付け不良などの作業ミスが起こりやすいです。まず畳のサイズを正確に計測し、畳表や縁のカットは余裕を持たせて慎重に行うことがポイントです。特に角や縁の仕上げ部分は見た目や耐久性に大きく影響するため、丁寧な作業が求められます。
また、畳表の張替えや裏返し作業中に畳床を傷つけないよう、専用の道具を使うことも大切です。作業前に流れをシミュレーションしておくことで、手順の抜けやミスを防ぐことができます。

DIY畳替えの安全対策と失敗しないコツ
DIYで畳替えを行う場合、安全対策を徹底することが失敗防止につながります。畳は意外と重量があり、持ち上げる際には腰や手を痛めるリスクがあります。作業は必ず複数人で行い、軍手やマスクを着用して怪我やホコリの吸い込みを防止しましょう。
また、畳表や縁の取り付け時に釘や道具を使用するため、周囲の安全確認も必須です。作業スペースを整理し、滑りやすい場所や障害物がないか事前にチェックすることで、事故やトラブルを防げます。
業者依頼と自分作業それぞれの違い

畳替えを業者依頼とDIYで比較するポイント
畳替えを検討する際、業者依頼とDIYのどちらを選ぶべきか悩む方は多いです。費用、手間、仕上がりの品質が主な比較ポイントとなります。業者に依頼した場合はプロによる施工で仕上がりが均一ですが、費用はDIYに比べて高くなる傾向があります。一方、自分で畳替えを行えばコストを抑えられますが、正しい手順や工具の準備、技術が必要です。
具体的な比較ポイントとしては、作業の難易度や畳表・裏返し・新調などの種類により適した方法が異なる点が挙げられます。例えば、畳表の表替えは比較的DIYでも対応可能ですが、新調や裏返しはプロの技術が求められることが多いです。失敗すると畳が浮いたり隙間ができやすいため、慎重に判断することが重要です。
また、畳替えを自分で行う場合には、ホームセンターで材料を購入できるものの、畳の寸法や部屋の状態を正確に把握しないと不具合が生じやすいです。業者依頼の場合は現地調査や見積もり、施工後のアフターフォローまで一貫して対応してくれる点も安心材料となります。

業者と自分作業の畳替え手順や仕上がりの違い
畳替えの手順は、大きく「畳表の表替え」「裏返し」「新調」の3種類に分かれます。業者依頼の場合、まず現地調査で畳の状態や部屋の寸法を確認し、最適な素材や施工方法を提案します。その後、畳の引き取り・運搬・施工・敷き込みまで一連の流れで丁寧に作業が進みます。
自分で畳替えを行う場合は、畳の取り外し・表替えや裏返しの作業・再設置という流れになりますが、専用工具や正しい手順を知っていることが前提です。例えば、畳表の張り替えは畳表と縁の固定、角の処理など細かな作業が多く、不慣れだと仕上がりにムラや隙間ができるリスクがあります。
仕上がりの違いとして、業者による施工は畳表の張り具合や縁の取り付けが美しく、耐久性にも優れます。DIYの場合はコストを抑えられる反面、部屋ごとに畳のサイズが微妙に異なるため、寸法調整や敷き方にも注意が必要です。失敗例として、畳が浮いたり隙間ができてしまう事例があるため、初心者は特に慎重な作業が求められます。

畳替え費用や作業日数で選ぶ判断基準
畳替えの費用や作業日数は、選ぶ方法や畳の種類によって大きく異なります。一般的に業者依頼の場合、6畳の畳表替えでおおよそ3万円から5万円程度が相場です。新調や高品質な素材を選ぶとさらに費用は上がります。一方、DIYで行えば材料費のみで済みますが、工具の購入やミスによる追加コストが発生する可能性もあります。
作業日数の目安として、業者に依頼した場合は事前の見積もりや畳の引き取りを含めて1日から2日程度で完了することが多いです。DIYの場合は作業に慣れていないと1日以上かかる場合や、複数日にわたることもあります。特に畳の枚数が多い場合や裏返し作業などは時間がかかりやすい点に注意が必要です。
判断基準としては、費用を抑えたい場合はDIY、仕上がりや耐久性、時短を重視する場合は業者依頼がおすすめです。また、畳の状態や使用年数によっては裏返しや表替え、新調のどれが適しているかも異なるため、専門家に相談して最適な方法を選ぶのが失敗を防ぐポイントです。

業者依頼のメリットとDIYの注意点を解説
畳替えを業者に依頼する最大のメリットは、専門的な技術による高品質な仕上がりと、アフターフォローの充実です。現地調査や見積もり、施工後のメンテナンスまで一貫して対応してくれるため、初めての方や時間がない方にも安心です。また、畳表や縁のデザイン選びもプロのアドバイスが受けられる点が魅力です。
一方、DIYで畳替えを行う場合は、費用を抑えられる反面、正しい手順や工具、材料の選定が不可欠です。特に畳の寸法測定や敷き方にミスがあると、畳が浮いたり隙間ができたりするリスクがあります。作業前には、畳替え方法の流れや注意点をしっかり調べ、必要な準備を行うことが大切です。
DIYに挑戦する際は、ホームセンターや専門店で材料を揃え、事前に手順を確認しましょう。作業後に異変があった場合は、専門業者に相談することも検討してください。失敗例を参考にしながら慎重に進めることで、満足のいく畳替えが実現できます。

畳替えで失敗しない業者選びと自分作業のコツ
畳替えで失敗しないためには、信頼できる業者選びと自分作業のコツを押さえることが重要です。業者選びの際は、実績や口コミ、見積もり内容を比較し、現地調査やアフターサービスの有無も確認しましょう。また、複数業者から見積もりを取ることで、費用やサービスの違いを把握できます。
自分で畳替えを行う場合は、事前準備が成功の鍵です。畳の寸法を正確に測り、必要な工具や材料を揃えることが基本となります。作業手順を事前にシミュレーションし、畳の状態や部屋の気候条件を考慮して作業日を決めると良いでしょう。特に湿気の多い時期は、カビや劣化防止のために換気や乾燥にも注意が必要です。
また、初めての方は畳表の表替えなど比較的簡単な作業から挑戦し、難易度の高い新調や裏返しは業者に相談するのがおすすめです。実際の利用者の失敗談や成功例も参考に、無理のない範囲で畳替えに取り組みましょう。